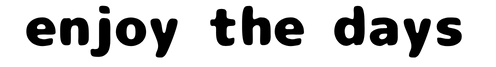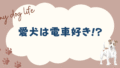日本各地で話題になっているのが熊被害ですが、愛犬家の間で被害がジワジワと増えているという話があります。
それは毒蛇マムシ!マムシは日本に広く分布する毒蛇で、特に今年は目撃情報が多いんです。
特に被害に遭っているのは散歩をしている愛犬。
マムシに噛まれて救急に駆け込むワンちゃんが増えています。
ではどんな場所で被害に遭いやすいのか、対策方法や応急処置の方法などを詳しくみていきましょう。
ぜひ最後まで見ていただき、マムシの被害に遭わないようにしましょう!
マムシについて

マムシはクサリヘビ科の毒蛇の一種で、日本全国(沖縄を除く)に生息しています。
全長は約40cmから65cm程度で、頭は三角形、灰褐色の色に暗褐色の輪状の斑紋が特徴です。
アカマムシと呼ばれる赤褐色型もいます。
活動時期と生息場所
マムシは春から秋(4月〜10月頃)にかけて活動が活発になります。
特に気温が下がる早朝などは、体温を上げるために日当たりの良い場所に出てくることがあります。
夜行性ですが、涼しくなった秋口でも遭遇する可能性あり。
水田の脇、小さな川辺、背の高い草むら、水辺の岩の間、竹藪などの湿地を好んで生息しています。
林道や河川敷、石が積まれた場所なども注意が必要!
犬が咬まれる状況
マムシはおとなしい性格ですが、犬が好奇心から匂いを嗅いだり、近づきすぎたりすることで咬まれることがあります。
散歩中に犬がマーキングや排泄のために草むらに入る際に遭遇しやすく、鼻先や足先など体の先端部分を咬まれることが多いです。
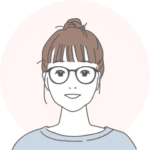
サムも河川敷や田んぼ道が大好きで、背の高い草むらにズンズン入りたがるんですよね。

マムシに咬まれた時の症状
犬がマムシに噛まれると、痛みから『キャン』と鳴いたり、足を噛まれた場合は足を引きずったりするため、飼い主さんが異変に気づきやすいです。
症状の例
人間と犬の違い
犬は人間と比べてマムシに耐性があると言われています。
その理由は明確ではありませんが、体温が人間より2〜3度高いことが、毒の酵素活動を抑える働きをしているのではないかと考えられているようです。
しかし、適切で速やかな処置がなければ、命に関わる可能性も。
対処方法
応急処置と予防策
愛犬がマムシに咬まれてしまったら、何よりもまずすぐに動物病院へ連れて行くことが最善の対処法!
動物病院へ向かう際は、愛犬をできるだけ安静に保ちましょうね。
興奮して心拍数が上がると、毒の回りが早くなる可能性があります。
咬まれた箇所を強く圧迫したり、毒を吸い出そうとしたりする行為は危険なので避けてください!
マムシの事故を防ぐには日頃の予防が大切
散歩場所は河川敷や草地、藪、水辺など、マムシが生息しやすい場所は避けましょう。
散歩中はリードをしっかり持ち、自由に動き回らせないように飼い主さんの目の届く範囲で行動させることが大切です。
マムシが活動的になる夕方から夜間、または早朝の散歩は特に注意が必要。
また、山や草むらに散歩に行く際は、ハーネスやブーツなどの防具を着用させることも有効です。
マムシ毒はたんぱく質を分解する作用があるため、皮膚の壊死や浮腫、出血を引き起こします。
動物病院での処置
咬傷の程度によりますが、動物病院では点滴、抗生剤、消炎剤、止血剤などが投与されることが一般的です。
犬のマムシ咬傷、その後の経過
犬がマムシに咬まれても、適切な治療をすればほとんどのケースで回復しますが、咬まれた部位や毒の量、犬の健康状態によって予後は大きく異なります。
死に至るケースはまれ
マムシの毒で犬が死亡することは稀です。
過去には、マムシに咬まれて死に至った症例は1例もないという動物病院の報告もあります。
しかし、決して油断はできませんね。
個体差や咬まれた場所、毒の量によっては重症化することもあり、輸血が必要になるケースも報告されています。
咬傷後の主な症状と注意点
マムシに咬まれると、咬まれた部位の強い腫れや痛み、内出血、皮膚の壊死が起こることがあります。
特に、以下のような症状に注意が必要。
毒液にはたんぱく質を分解する作用があるため、咬まれた部位の皮膚や組織が壊死したり、そこから化膿したりする二次感染のリスクがあります。
獣医さんによっては、傷口の壊死のケアを重視。
傷が治った後でも、肝機能に異常が見られる症例も報告されています。
毒の作用によって、咬まれた部分の毛が抜け落ち、元通りに生えてこない可能性も。
回復までの目安
回復までにかかる時間は様々ですが、腫れは数日から1週間ほどで改善していくことが多いです。
しかし、毒が完全に抜けるまでには時間がかかるため、獣医さんの指示に従って、内服薬の継続や定期的な通院が必要。
回復が遅れる、または注意が必要なケース
咬まれてから動物病院へ行くのが遅れると、その分、毒が体内に広がり、回復期間が長くなる可能性があります。
顔面や頭部を咬まれることが最も多く(56%)、次いで前肢(21%)、後肢(19%)と報告されています。
毒によって毛根が損傷した場合は、咬まれた部分の毛が抜け落ち、元通りに生えてこない可能性も。
完治後も毛が生えない場合は、長期的なケアが必要になることもあります。
回復までの期間はあくまで目安であり、愛犬の状況によっては獣医さんと相談しながら治療を進めることが非常に重要。

終わりに
愛犬は人間よりもマムシの毒に耐性があると言われることもありますが、決して「大丈夫」というわけではありません。
子犬や老犬、体の小さい犬は特に重症化しやすいので注意が必要です。
早期の適切な治療が、愛犬の命と健康を守るために何よりも大切ですね。
私たち飼い主が少し気をつけてあげることによって、愛犬をマムシの危険から守ることができますので、この時期も注意を怠らずに、愛犬との散歩ライフを楽しみましょう!